地方自治体の議会で議員が欠けたときその空席を埋めるために行われるのが補欠選挙です。
都道府県議会や市区町村議会では、議員の辞職や死亡などで議席が空くと新たな選挙が実施されます。これが補欠選挙。
しかし、補欠選挙のルールは議会の種類によって異なりタイミングや条件にも特徴があります。この記事では、地方選挙の補欠選挙について概要から具体的な仕組みまでわかりやすく解説します。
補欠選挙の概要
補欠選挙とは、議員の任期途中に欠員が生じた場合にその議席を補充するための臨時的な選挙です。
地方議会では、都道府県議会や市区町村議会の機能を維持し、地域住民の代表が途切れないようにすることが目的です。公職選挙法に基づいて規定されており通常の選挙とは異なり特定の選挙区や条件に限定して行われます。
- 実施のきっかけ: 議員の辞職、死亡、失職(当選無効や資格喪失など)。
- タイミング: 知事選挙や首長選挙(市区町村長選挙)と同時に行われることもあるが(いわゆる便乗選挙)、単独での実施もあり。
- 例外: 任期満了の6ヶ月以内に欠員が生じた場合、次の通常選挙で対応するため補欠選挙は行わないことも。
そして同じ地方選挙でも県議会の補欠選挙と市区町村議会の補欠選挙では条件が異なります。
都道府県議会の補欠選挙
都道府県議会の補欠選挙について解説します。
都道府県議会の選挙区と定数の特徴
都道府県議会では、県内が複数の選挙区に細かく分けられています。例えば、東京都議会は42選挙区、埼玉県議会は52選挙区と、地域ごとに区分けされます。各選挙区の定数は人口に応じて異なり、1人から10人程度ですが1~5人が一般的です。
- 定数1人: 島嶼部や人口の少ない地域(例: 東京都の大島選挙区)。
- 定数2~10人: 人口密集地(例: 東京都世田谷区は8人、大田区は11人)。
補欠選挙の実施条件
県議会の補欠選挙は、選挙区ごとの定数に基づいて条件が定められています。1人区の場合はその1人が欠けた時点、2人以上の選挙区の場合は2人以上の欠員が出た時に補欠選挙を行います。
| 選挙区の定数 | 補欠選挙の条件 |
|---|---|
| 定員1人 | 1人欠けた時点で実施 |
| 定員2人以上 | 2人以上の欠員が生じた場合 |
補欠選挙が行われる理由と背景
都道府県議会では選挙区の定数が少ないため「2人以上の欠員が出た場合は補欠選挙を行う」という条件が設定されています。もちろん定数が1人の場合は1人の欠員で補欠選挙が行われます
- 定数1人の場合: 欠員が1人でも発生すると、その選挙区の代表がゼロになるため、即座に補欠選挙が必要です。
- 定数が複数の場合: 1人欠けただけでは残りの議員で代表性を維持できるとされ、2人以上の欠員で議会機能に影響が出ると判断されます。
- 便乗選挙:同地区で選挙が行われる場合は欠員が規定より少なくても補欠選挙が行われる場合があります(もちろん欠員が無ければ行われません)。
具体例
具体例を見ていきましょう
- 東京都議会で新宿区選挙区(定数4人)の議員が2人辞職した場合、その選挙区だけで補欠選挙が行われます。
- 一方、島嶼部の選挙区(定数1人)なら1人欠けた時点で実施対象となります。
- 新宿区選挙区(定数4人)の議員が1人辞職した場合は2人以上ではないので補欠選挙は行われませんが東京都知事選挙がある場合は補欠選挙(いわゆる便乗選挙)が行われる場合もあります
他にも東京都知事選挙に新宿区選挙区の都議会議員が立候補する場合にも欠員が生じるので東京都知事選挙と同時に補欠選挙が行われるケースもあります(これも便乗選挙のようなもの)。
市区町村議会の補欠選挙
市区町村議会の補欠選挙についても解説します。
選挙区と定数の特徴
市区町村議会は、基本的に「市町村全体が1つの選挙区」(大選挙区制)です。定数は人口規模に応じて設定され、10~30人程度が一般的です。
- 中規模市: 定数20~30人(例: 定数24人の市議会)。
- 小規模町村: 定数10人以下(例: 定数8人の町議会)。
補欠選挙の実施条件
市区町村議会の補欠選挙は、全体の定数に対する欠員の割合で決まります。6分の1以上の欠員が出た場合に補欠選挙が行われます。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 欠員数の基準 | 定数の6分の1を超えた場合 (定数24人なら5人以上、定数18人なら4人以上) |
補欠選挙が行われる理由と背景
- 割合基準の採用: 定数が多く、1~2人の欠員では議会全体の機能に大きな影響がないため、6分の1という割合で線引きしています
- 便乗選挙:同地区で選挙が行われる場合は欠員が規定より少なくても補欠選挙が行われる場合があります(もちろん欠員が無ければ行われません)。
都道府県議会よりも補欠選挙が行われる条件が厳しく見えます。これは市区町村選挙ではもともと定数が大きいからだと考えてください。またコスト削減目的だとも考えてください。 少数の欠員で頻繁に補欠選挙を行うのを避け必要最小限に抑える目的です。
具体例
具体例を見ていきましょう。
- 定数24人の市議会で、議員が5人辞職した場合は6分の1(4人)を超えるため補欠選挙が実施されます
- 一方定数24人の市議会で3人欠けても条件に満たないため様子見となります
- 例外としては大阪市のケース。政令都市ということで区に分けていますが定員が5人以下のところが多い。そのため1人でも欠けたら定数の6分の1以上が欠けることになり補欠選挙が行われます。
- 条件に満たなくても市長選挙が同地区で選挙が行われる場合は補欠選挙(いわゆる便乗選挙)が行われるケースも
現実には定数の6分の1以上が欠けることはあまりないのでその条件で補欠選挙が行われることはほとんどありません。補欠選挙が行われるケースは便乗選挙になることが多いです。
国会議員の補欠選挙
ちなみに国政選挙では選挙区の定数が少ないので以下のようなケースで補欠選挙が行われます。地方選挙とは条件が異なります。
- 衆議院小選挙区では1人の欠員が生じたとき
- 参議院選挙区では通常選挙における当該選挙区の議員定数(すなわち改選議席数)の4分の1を超えるとき(東京都選挙区、神奈川県選挙区、埼玉県選挙区、愛知県選挙区及び大阪府選挙区で2人、それ以外の選挙区では1人の欠員が生じたとき)
- 衆議院比例代表および参議院比例代表では、再選挙の対象となる当選人不足数をあわせて定数の4分の1を超えるとき(基本的には繰り上げ補充となるのでこれまでにこのケースで選挙が行われたことはありません)
基本的に国政で補欠選挙が行われるのは小選挙区のみと考えるといいでしょう。欠員が出たら選挙が行われる選挙区が多い。一方で比例は繰り上げ充当されるので選挙が行われることはありません。
まとめ
地方選挙の補欠選挙は、都道府県議会と市区町村議会で異なる仕組みを持っています。
県議会は選挙区が細かく分けられ、定数が少ないため「1人欠け(定員1人)」または「2人以上欠け(定員複数)」という人数基準で補欠選挙が行われます。
一方、市区町村議会は1選挙区で定数が多く、「6分の1超」という割合基準が適用されます。この違いは、県議会が選挙区ごとの代表性を重視し、市区町村議会が全体の機能維持を優先する方針によるものです。補欠選挙は地域の声を議会に届ける重要な仕組みですが、コストや効率を考慮した現実的な運用が特徴と言えるでしょう。
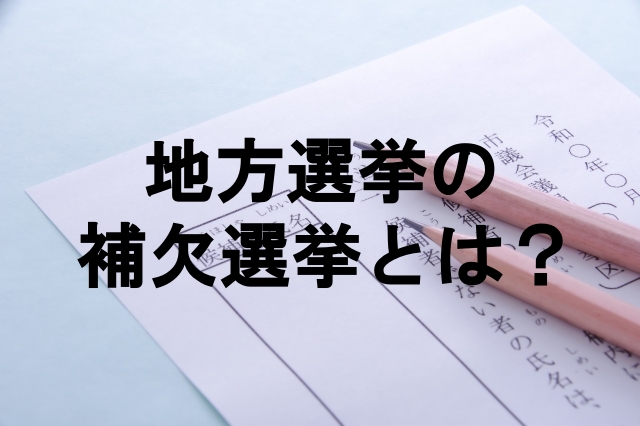
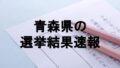

コメント